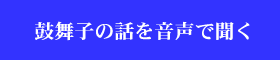2004年9月16日〜22日 アメリカ公演を行います

陣頭指揮兼広報の石田教頭
県立平塚聾学校高等部専攻科『鼓舞子』(こぶし)にまつわるドラマティックな話は枚挙に暇がない。しかし、それについての詳細は、石田邦彦先生がお書きになった文章(こちらをクリック)に譲ることにしよう。
彼らについて書く際、まず、ろう学校という存在について、きちんと知るべきだと考える。
実は、私(管理人)は平塚江南高校で思春期(?)を過ごした。そして、平塚ろう学校は徒歩1分という距離にありながら近くて遠い存在であった。
自転車での通学路、毎日、私はろう学校の前を通っていたが、その中にいる同年代の生徒たちと挨拶すら交わしたことがなかった。それを苦痛に思ったことも、不思議に感じたこともなかった。
ま、自らのことで精一杯であった、と言えるのかもしれないが。
つまりは、「自分たちとは違う世界」の人たち、と無意識に受け止めていた、ということになろうか。
一般論として、健常者というのは、なかなか障害者の世界を知り得ない。また、何か特別な理由がない限りは、知ろうともしない。私もそうであった。
彼らのことを取材しようと思ったきっかけは、一冊のマンガであった。
皆さんがどれほどご存知であるかはわからないが、『遥かなる甲子園』(原作・戸部良也氏、マンガ・山本おさむ氏)という本があり、私はこれにいたく感動した経験がある。
(確か、映画にもなったと記憶している)
概要としては、沖縄で風疹が流行った時に生まれた聴覚障害児たちと熱意あふれる教師たちが、高野連の定める規定を打ち破って、ろう学校に硬式野球部を立ち上げ、懸命に甲子園を目指す、という事実に基づいた作品である。
この作品中には、聴覚障害を持つ子供たちの葛藤や、障害児を持つ親の苦悩が実に丹念な筆致で描かれている。さらには、聴覚障害者に対する教育の問題、周囲の無理解といったことも含め、マンガとしては異例の世界を扱ったものと言えるだろう。
このマンガを読もうとした直接の動機は、教え子の中に、それほど重度ではないと思われるが、聴力に障害を持ち、授業を常に最前列で受け、わからないことは筆談も含め、必死に質問する女の子がいたからだ。やはり、自らと何かしらの関わりがないと、そういった関心がわきづらい、ということは否めないかもしれないが...。
そういった素地があって、さらに、今年の4月、私が所属する茅ヶ崎ロータリークラブの会合で石田教頭が「学校関係者・市民・行政その他の善意によるアメリカ公演が同時多発テロによって中止になった」という話をされたのを受け、『部活.ネット』での取材を決意したわけである。
本職で教育に関わりながら、私は取材するその日まで、ろう学校の仕組みというものをよく知らなかったのだが、石田教頭が、ひじょうにわかりやすく説明してくれた。
平塚ろう学校は、幼稚部・小学部・中学部・高等部から成り、高等部は本科3年(通常の高校に通う年齢に相当)・専攻科2年(産業工芸・被服・印刷・理容の4科。専門学校に相当する)である。
(「鼓舞子」のメンバーは、高等部専攻科の生徒とそのOBである)
障害の有無は、生後すぐに判明する場合もあるが、聴覚については、自閉症などと同様、1歳〜2歳にかけて、わかることが多い、という統計がある。
細かなことは省略させてもらうが、ろう学校に入るような子供たちは、概ね100デシベル以下の聴力(ガード下にいて、列車の通過音が聞こえない程度)という場合が多い。
(個人差はあります)
音のない世界というのを健常者が想像することは大変に難しい。しかし、彼らは、周囲の音は勿論、自分の発した声を聞くこともままならないわけで、その影響は、他者とのコミュニケーションを困難にする。
子供というのは、親などの近くにいる存在から、音声によって言葉を覚えてゆくのが普通であるから、その機会を失うだけでも、どれほど大変か、理解はできる。
聴覚障害を持つ子供たちに対する教育で、最も重要になるのが「言葉」である。
言葉は、単に他者とのコミュニケーションを図る道具、という側面だけでなく、「学習する」或いは「思考する」ためにも不可欠なものである。
私が深いところまで書くことは到底できないが、大別すると「残存機能の活用」「読話(読唇術)」 「筆談」「指文字」「手話」といったものになる。これらを複合させて、健常者を含む他者との意思疎通を図ることになる。
これらを習得するだけでも大変であるが、さらには「発音・発語」も求められる。一般社会の一員として社会生活を営む上で、とっさの時には音に出して表現することも必要になるからである。
ろう学校というのは、そうした教育を施すだけでなく、学力をつけ、情操面での指導もし、社会に出てやってゆけるだけの技術も身につける場なのである。
こうした背景を知っているかどうかで、『鼓舞子』のメンバーたちを見る目も変わってくることであろう。









さて、前置きが長くなったが、『鼓舞子』について、ようやく書かせてもらう。
前述したように、『鼓舞子』は平塚ろう学校高等部専攻科の現役生とOBから成立している。現在、専攻科に在籍する15人のうち、9人が『鼓舞子』のメンバーである。
『鼓舞子』が生まれたきっかけは『拳』(こぶし)であった。
平塚ろう学校は平成7年の創立70周年に向けて、平成5〜6年に校舎の建て替えを進めていた。当時の在籍生たちは、グラウンドに仮設されたプレハブ校舎で授業を受けることになった。
で、そのことが学校が荒れる原因となったのだ。
一般的には想像しづらいが、補聴器をつけている子供たちにとって、金属の壁に囲まれていることは、本来聞こえなくてもよい音が聞こえ、相当イライラするもののようだ。
そんなある日、イライラの昂じた専攻科の生徒が、音楽の徳田宗千(むねゆき)先生をぶん殴ってしまった。それを止めに入ったのが、現・教頭の石田先生であった。
殴られた徳田先生が、石田先生に向かって、「生徒の気持ちを落ち着かせるために、一緒に和太鼓を教えませんか?」と病床で提案し、それが現在の『鼓舞子』の原型となったのであった。
当時、平塚ろう学校の部活と言えば、男子は野球、女子はバレーボールというのが当然の如くに受け止められていたようだ。実際、野球もバレーも関東ろう学校大会で何度も優勝している。
しかし、それは高等部本科の18歳までであり、専攻科には本格的な部活動が存在していなかった。
聴覚障害があるといっても、体力は普通の若者と何ら変わらない彼らが、石田・徳田両先生の熱心な指導に、やがて心を開いて、真剣に和太鼓にのめりこんでいったのは、必然であったと言えるだろう。
当初は、併設された寄宿舎に、「目覚まし用」として置かれていた太鼓が一つあっただけであったが、校舎建て替えの際に、県からいくつかの太鼓を備品として提供されるという幸運もあり、『鼓舞子』は活動を広げていった。
そうした地道な積み重ねが、2001年9月、アメリカ公演への招聘という形で花開こうとしたわけだが、9.11の同時多発テロの影響で、中止になってしまった。部員たちの落胆は十分に想像がつこうというものだ。
しかし、世の中、捨てる神あれば拾う神あり。今度は別のルートからアメリカでの演奏を、という依頼が来たのだ。
指導の先生方、部員は大喜び。しかも、今回は他の団体と一緒なので、太鼓を運ぶ費用も心配しなくて済む、というオマケつき。
(前回は渡航費・太鼓の輸送費だけで400万円集めなければならなかった!)
そんな『鼓舞子』の活動を訪ねさせてもらった。
練習場に入れてもらった。9人の部員たちは、少し緊張したのか、鐘も太鼓もタイミングが狂いだす。すると、石田教頭がすかさず生徒の前に出て、大きくばちを振って、「このタイミングだよ」と体で見せる。生徒たちのタイミングが合い始める。
今度は、岩崎守男先生と杉山清子先生も加わって、賑やかになってゆく。太鼓の低音が、「波」となって我々にも伝わる。きっと生徒たちも、この「波」を体感して、リズムを合わせてゆくのであろう。
岩崎先生は赴任3年目。国語の先生である。
「部活で一生懸命やっていると聞いて、僕自身が勉強以外のことで一緒にやれることを探していたところだったので、入れてもらったんです。最初にアメリカで演奏する予定だった子たちの真剣さに引きずられたと言うか...。勉強ではなかなか心が通い合いませんが、太鼓をやっていると、心が通うというのを実感しますね。」
とのこと。
杉山先生はろう学校で15年目。被服の先生で、平成7年から彼らと一緒に活動している。
「太鼓を叩く姿がカッコイイなぁと。それに、ステージの準備、後片付けも一生懸命やっているのを見て、子供たちが成長してゆくのがわかって楽しいです。」
創設者の一人である徳田先生は今年、養護学校に転任されたが、アメリカ公演には帯同して、篠笛を吹く。映像(こちらをクリック)で見てもらえればわかるが、彼の笛は音色が安定していて、『鼓舞子』の面々の太鼓を引き立たせる。
あまりに上手なので、石田教頭に聞いてみると、音大でフルートを専攻していたそうだ。どおりで...。
生徒たちにも質問してみた。
(手話での通訳は石田教頭にお願いしました!)
Q:なぜ太鼓をやろうと思ったのですか?
「カッコイイと思った」
「大きな舞台に立つという夢があるから」
「アメリカに行ってみたかった」
「先生が太鼓叩いているのを見て、カッコよくて、もてそうだと思った」(爆笑)
Q:やめたいと思ったことはないですか?
「....ある」
「アメリカ公演までは絶対にやめない!」
「負けず嫌いで、自分が一番だと思ってるからだろ」(爆笑)
先生方の話を総合すると、誰もが一度ならず「やめたい」と思うそうである。それはどんな部活でも似たりよったりかもしれませんなぁ。
Q:太鼓やってて何が楽しいですか?
「皆で練習していて、一つになれた時に嬉しい」
「ノレた時」
Q:アメリカ公演ではどんな演奏をしたいですか?
「大和魂を見せたい!」
石田教頭「ふんどしとかつけるか?」
「それは嫌だ!」(大爆笑)
ちなみに、ふんどし姿での演奏は禁止だそうです。
我々には手話が通じないと思ったのか(実際、通じないけど)、皆、発語してくれた。中には、「君、本当は聞こえているんじゃないの?」と思いたくなるほど上手な子もいた。訓練の成果だね。
専攻科1年生3名、2年生6名。彼らは、入学して以来、ずっと同級生である。おそらく、仲たがいしたこともあっただろうが、聴覚障害者にとっては一大チャレンジとも言える和太鼓を通じて、心を一つにしてゆくことだろう。
和太鼓の「和」は、日本ということを意味するだけでなく、『鼓舞子』たちの「和」でもあるのだ。


障害者もしくは障害者と何らかの形で関わっている人が書いた文章を扱う「NHK障害福祉賞 実践記録入選集」に掲載され、のちに俳優・前田吟氏の朗読によるテレビ放映もされたものです。是非、ご一読下さい。
校門を入ったところのすぐ横に、一本のまだ若い桜の木が申し訳なさそうに少々の花弁をつけて咲いた。
私は、しばらくその桜の木を眺めていた。この木が大きくなるまであと何年かかるだろう。
十五年前、私がはじめて、このろう学校の門をくぐったとき、そこには春先の満開時、みごとな桜花をつけた老木があった。
このろう学校を巣立っていく生徒たち誰もが、みんなその老木の下で記念写真を撮る光景が三月の心温まる絵になって私の脳裏に焼き付いている。
新しく校舎を建て替えるとき、誰も知らないうち、その桜の木は、根本から切り倒されて姿を消していた。
「なにも、ろう学校などに転勤することはないじゃないか」。普通高校の体育教師であった私がろう学校への異動希望を出した時、勤めていた学校の校長は言った。
私がその学校の中堅どころとして、担任をしたり、学校行事のいくつかをまとめていたりした時期だった。自分の置かれていた立場も分かってはいたが、気持ちの高まりを抑えることはできなかった。
私がろう学校への異動を決意したのは、ある一日の出来事がきっかけだった。以前からの知り合いで、先輩の体育教師K先生がすでにろう学校へ勤めていて、ある時「ろう学校の運動会を見に来ないか」と誘われた。私は、ろう学校の運動会とは、どんなものだろうという、半分好奇心も手伝って、日曜日の一日、気軽な気持ちで出かけてみた。
そしてそこで、聴覚にハンディを持っている子どもたちが、その障害を感じさせないほど、生き生きとした活気あふれる運動会を展開しているのを見た。
どの子どもたちも一生懸命、演技し競技していた。
私は、先輩の先生に勧められるままに、一五〇〇メートル競走に飛び入り出場した。中学生、高校生たちが、私のほうを見て何やら手話を交わしている。どうやら「あいつは誰だ?知ってるか。自分たちよりも速いのか?」と言い合っているようすが見えた。
スタートをしてすぐ高校生の一人が飛び出した。私はその彼を追いかけ、終始肩を並べて走り、ゴール間際は二人のデッドヒートになった。彼が前に出る、私が前に出る、また彼が。
見ているほかの子ども達や保護者は総立ちで応接していた。そして、胸一つ差で私は彼に負けてしまった。子どもたちは次々とゴールに飛び込んでくる。私は一位になった生徒だけでなく全員の生徒と握手を交わした。さわやかだった。みんなキラキラした汗を流していて、強く手を握りかえしてきた。
ことばが通じあわなくとも温かいものが流れた。先輩の先生が私のところに近寄ってきた。
「ゴールのところで力を抜いただろう?」
「いえ、必死でしたよ、目一杯です」
「いーや違うな。長距離ランナーのあんたがあそこで負けるはずがない。どこかで生徒に勝たせてやろうとしなかったかい。勝負にこだわって言うんじゃないが、ウチの生徒たちはね、自分を負かすぐらい強い人がそばにいてくれて、その人を目標にしてがんばるという気持ちがとても強いんだ。だから遠慮しないで本気で走っていいんだよ。いやむしろ、そのほうがありがたいんだよ」と言われて私は動揺した。
たしかに私はゴール付近、頑張りはしたものの、100パーセントの力を出し切ったかと聞かれると、自信を持って答えられないものが残っていた。それは私の中にハンディを持っているものに対しての、どこか手加減をする気持ちが働いていたのかも知れない。
私は、校長の説得に耳をかさず、ろう学校に異動希望を出した。
そして希望は叶えられ、四十三才でろう学校の体育教師になった。
考えていた以上に、厳しい日々もありはしたものの、生徒たちと通いあうものの中に、自分の教師生命をかける覚悟に迷いはなかった。毎年、十二月の校内マラソン大会では、勤めてから十五間、一度も手を抜いた走りをしたことがない。生徒たちは、日常のいろいろなところで私を見ていた。私を何でも頑張る先生と見ているようだった。そしてそれは、私自身がこれまでの教員生活で一貫して持っていた自分のスタイルであり、それがこのろう学校でも出せていることに幸せを感じていた。
ある時、音楽室の前を通った。身体の大きい生徒が険しい顔をして仁王立ちしていた。
そばに、音楽の教師が仰向けに倒れていた。
私は、とっさに「やったな」と直感して、音楽室に入り、「おまえがやったのか?」と手話で話しかけた。彼は、「おれがやった!」とこぶしを挙げて胸を張った。先生を殴り倒して興奮している様が見えた。
幼稚園生の年令から、このろう学校にいる彼は、高校生になってからの自我の目覚めに、時として自制心を失って粗野な行動をとることがあった。私は彼が「おれがやった」と言って胸を張ったその瞬間、「何をしてるんだ、力が強いってことはそういうことに使うんじゃない」私がいつに見せない真顔で叱ったものだから、彼は、すぐにおとなしくなった。
倒れていた先生は、ろう学校で音楽を教えるT教諭だった。大事を取って、病院で検査を受け、しばらくベッドで安静にしていた彼が急に私に向かって言った。「先生、子どもたちと太鼓の演奏をしてみませんか」と。彼はそれまでも音楽の授業で生徒に和太鼓をこつこつと教えていた。太鼓のような打楽器の低い音を感じ取る生徒もいて、ろう学校では、有効な音楽の教材の一つだった。
私はすぐに同意し、それが生徒たちとともに、和太鼓演奏に取り組むきっかけになった。
しかし、もとより聴覚にハンディを持つ生徒たちに、音の強弱とリズムを刻むことを教えるのは、かなり難しいことではあった。
長野県のプロ太鼓集団が夏に行う合宿練習会に生徒を連れて参加した。
一曲の演奏曲を覚えることは遅々として進まず、大きな壁を感じた。それでも、音楽のT教諭と私はあきらめずに、粘りづよく挑戦した。太鼓の振動音を全身でとらえよう。敢えてくれる人の身体の動きをよく見よう。バチのふりかぎしをまねてみよう。とアドバイスした。そして、一つの曲の演奏が完成した。「ぶちあわせ太鼓」、はじめて生徒と私たちが演奏を合わせることができた曲だ。これは、以来約十年の月日が流れ、いくつかの曲をこなせるようになった今も、演奏会では、かならず最後に演奏する私たちの原点の一曲である。グループの名も、太鼓のまわりで舞う子どもたちという意味で和太鼓同好会『鼓舞子』(こぶし)と名付けられた。部員三名、顧問三名。初めのころは、学校の近くの商店街での演奏。太鼓も、たった一つ。それでもろう学校の生徒が太鼓を打つというので、地元の人は見に来てくれ応接してくれた。
太鼓をリヤカーに乗せてどこへでも行った。まるで旅芸人のように。
そのうち、太鼓をやろうとする生徒が四人、五人、七人と増えていった。太鼓の数も、私たちの活動を応接してくれる方々から寄贈を受け、三台、五台、七台、と増えていった。今では大小合わせて、二十台ほどの太鼓がそろった。生徒も十五、六人の同好会員がそろった。それぞれが、自信を持って打ち上げる太鼓の演奏に、たくさんの人が拍手を送ってくれる。その拍手の波は、このろう学校を巣立っていく生徒にとって、かけがえのない財産となって胸の奥に残る。
年間三十回を超す演奏活動をこなし、時に、県民ホールなどの大舞台で、時に、老人ホームの施設で。どんなところでも、どんな人たちの前でも生徒たちも私たちも、常に一生懸命の演奏を披露した。
生徒たちは、全身耳をにして、太鼓の音を感じ取り、仲間の動きから目をはなさず、最後の最後まで気をぬかず演奏をした。その懸命に太鼓を打ち上げる姿に、多くの人がかならず感動と激励の拍手を送ってくれた。
ある時、一つのニュースが舞い込んだ。それは、学校が立地している平塚市が数年前に姉妹都市を結んだ、アメリカのローレンス市から五十人ほどの友好団を迎えるとき、その歓迎レセプションの席上で私たちの「鼓舞子」の演奏を依頼したいという連絡が入った。
その話に鼓舞子のメンバーは大喜びして練習にも熱が入った。
そしてその当日、十五人ほどの生徒は、いつもと同じように力いっぱいの演奏をした。
すでにいつもの場数を踏んでいる生徒たちは、ほとんど失敗なしに演奏でいるようになっていた。
二十分ほどの演奏が終わり、顔から流れる汗の中でおおぜいの人々の拍手を見た。外国の人たちにも喜んでもらえた。
うれしさに全員が満面の笑みと満足感あふれる顔をしていた。そして、このあと学校あげておどろくビッグな話が舞い込んでこようとは、誰も想像していなかった。
一通のメールをキャッチした先生が私のところに走ってきた。
「先生、鼓舞子に、アメリカに来てくれませんかですって」
「えっ、アメリカって、外国のアメリカ?」と私はトンテンカンなことを言い、次の瞬間、「やったー、やったね。すごいね」とはしゃぎ回ってしまった。生徒に伝えると、これまた大騒ぎ。中にはキョトンと信じられないという顔をするものもいた。あの時、歓迎レセプションで太鼓を演奏した時、友好団の中の一人で、アメリカ・カンザス州で行われるジャパンフェスティバル(日本祭)の実行委員長をしている人がいて、その人が、私たち「鼓舞子」の演奏を是非、アメリカで、とメールを送ってきたのだった。
私は、これはすごいことになったぞと、しばらく興奮がおさまらなかったが、メールをよく見て冷静になると、大変な壁があることに気がついた。つまり、メールには、アメリカに来ていただければ、むこうでの滞在費、移動費などはすべて実行委員会で持ちますが、太鼓の空輸・十人分の渡米に関しては、学校側でお願いしますとある。旅行社に見積もりを出してもらってびっくり。太鼓の空輸、十人分の渡米費、合わせて約四百万円がはじき出された。この話が舞い込んだのは、二〇〇一年、年明けの一月で、ジャパンフェスティバル(日本祭)はその年の九月に予定されていた。
それから始まった約八か月間の私たちの必死の資金集めは、今では語り草になっているが、演奏依頼を受けたところは、全部出演して、募金を呼びかけた。私たちに、土曜日も日曜日もなかった。生徒たちや私たちの祈るような呼びかけに市民のたくさんの人々や同じ障害児校の先生方、そして行政である障害児教育課も県財政逼迫の中、引率教員に最大限の旅費支給を決断してくれた。このように多くの人々が善意の力を結集してくれて、渡米直前に、すべりこみで資金のめどが立ち、ろう学校の生徒によるアメリカ公演という夢の舞台が、目の前に来た。
二〇〇一九月十一日、私たち「鼓舞子」は、まだ見ぬアメリカへと旅立つところまで来た。出発の日の朝、よりによって台風が上陸してしまった。大雨の中、成田空港はごったがえしていた。成田を飛び立つ飛行機は軒並み、その出発を見合わせたり、遅れて出発いう状況にあった。私たち「鼓舞子」のメンバー十一人をのせたノースウエスト機も予定時間を三時間半も遅れて出発した。そしてこの遅れが、あとで重大な運命の分かれ道になろうとは誰も予想すらしていなかった。
機内の人となったわれわれは、アメリカ公演のことを考えると胸が高鳴ったが、長旅の中で、うとうとしていた。私は、しばらく目をつぶった。そして、機内のアナウンスで目が覚めた。
あと二時間ほどでアメリカに着こうとする時だった。突然の機内放送はこう流れた。「当機は、安全上の理由から、カナダ・バンクーバー空港に着陸します」と。
私は、なぜ?と思った。生徒たちも、どうしたの?と私に向かって指を振っている。私は説明できないまま、しばらく待ってて、としか指示できなかった。
その時、アメリカ本土、ニューヨーク貿易センタービルに旅客機が突っ込み、史上最悪の同時多発テロ事件が勃発していようとは、思いもよらなかった。
カナダ・バンクーバー空港に降り立った私たちは、空港のテレビに何度も映し出される衝撃の映像が、はじめ誰もが、よくできた映画のワンシーンだと思った。
状況が次第に鮮明になり、今、自分たちが大変な事態の中にいることが、刻々と分かってきた。みんを言葉が少なくなった。
一つ間違えば、私たちの搭乗機が、その渦中に巻き込まれた可能性もなくはなっかったことを思って、ますます口が重くなった。
日本を出発する時、台風下の荒天が幸いした。三時間半の遅れによって、アメリカ本土への着陸ができない状況がむしろ、私たちを助けてくれた。
あとで分かったことだが、アメリカ本土に着陸した飛行機は、アメリカ全土の空港が閉鎖されたため、帰りの便もままならない状況でかなりの日数、滞在を余儀なくされたそうである。
私たちは、バンクーバーに三日間足止めされただけで、運良く、台北回りの帰路便に乗り込むことができた。たくさんの善意の人々の援助によって目の前まで来たアメリカ公演が、一瞬のうちに消え去ってしまった。
日本祭も中止になり、私たちは砂をかむような思いで、日本に帰ってきた。
バンクーバーでは、気丈に振る舞っていたメンバーだったが、成田に着いて、迎えに来ていた母親の顔を見たとたん、一人の女の子が、大粒の涙を流して泣いた。どれほど不安辛かっただろう。どれほど不安だっただろう。生徒も、私たちも口には出さなかったが、日本を離れての心細い思いはみんな同じだった。
あれから半年、すっかり立ち直った「鼓舞子」は、さらにむずかしい曲に挑戦し、その演奏の幅を広げている。
あいかわらず、いろいろなところから出演依頼が来て、どんな時にも全力の演奏を心がけている。
以前にもましてその演奏は力強く、みんなの心を揺さぶるようになっていた。
そんな時、また一通のメールが届いた。
“「鼓舞子」の皆さんを再びアメリカに招へいします。”と。
私たちの夢は、まだ終わっていない。